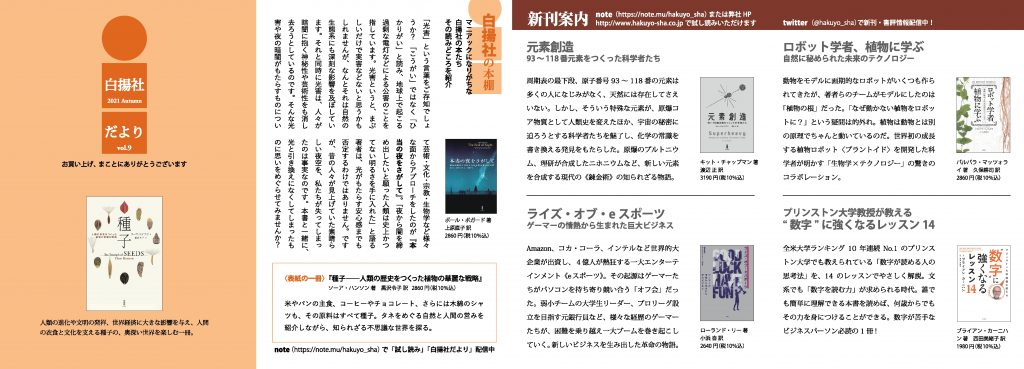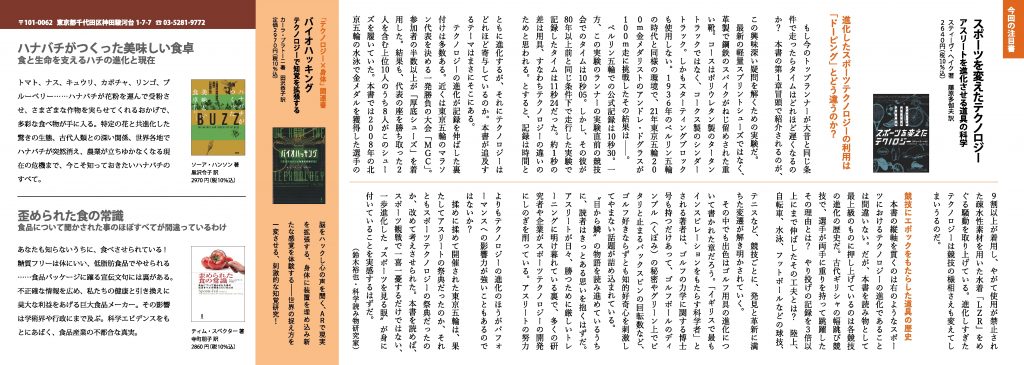科学読み物研究家・鈴木裕也の書評で読む『スポーツを変えたテクノロジー』

一般向けポピュラーサイエンス読み物を読み漁り、書評を書くライター・鈴木裕也さんが選んだ、イチオシの本を紹介するコーナーです
(白揚社の書籍に挟んでいる「白揚社だよりvol.9」からの転載)
◆
進化したスポーツテクノロジーの利用は
「ドーピング」 とどう違うのか?
もし今のトップランナーが大昔と同じ条件で走ったらタイムはどれほど遅くなるのか? 本書の第1章冒頭で紹介されるのが、この興味深い疑問を解くための実験だ。
最新の軽量スプリントシューズではなく、革製で鋼鉄のスパイクがねじ留めされた重い靴。コースはポリウレタン製のタータントラックではなく、コークス製のシンダートラック。しかもスターティングブロックも使用しない。1936年のベルリン五輪の時代と同様の環境で、21年東京五輪200m金メダリストのアンドレ・ドグラスが100m走に挑戦したその結果は――。
ベルリン五輪での公式記録は10秒30。一方、この実験のランナーの実験直前の競技会でのタイムは10秒05。しかし、その彼が80年以上前と同じ条件下で走行した実験で記録したタイムは11秒24だった。約1秒の差は用具、すなわちテクノロジーの違いのためと思われる。とすると、記録は時間とともに進化するが、それにテクノロジーはどれほど寄与しているのか。本書が追及するテーマはまさにそこにある。
テクノロジーの進化が記録を伸ばした裏付けは多数ある。近くは東京五輪のマラソン代表を決める一発勝負の大会「MGC」。参加者の半数以上が「厚底シューズ」を着用した。結果も、代表の座を勝ち取った2人を含む上位10人のうち8人がこのシューズを履いていた。本書では2008年の北京五輪の水泳で金メダルを獲得した選手の9割以上が着用し、やがて使用が禁止された疎水性素材を用いた水着「LZR」をめぐる騒動を取り上げている。進化しすぎたテクノロジーは競技の様相さえも変えてしまいうるのだ。
競技にエポックをもたらした道具の歴史
本書の縦軸を貫くのは右のようなスポーツにおけるテクノロジーの進化であることは間違いない。だが、本書を読み物として最上級のものに押し上げているのは各競技の進化の歴史だ。古代ギリシャの幅跳び競技で、選手が両手に重りを持って跳躍したその理由とは? やり投げの記録を3倍以上にまで伸ばしたその工夫とは? 陸上、自転車、水泳、フットボールなどの球技、テニスなど、競技ごとに、発見と革新に満ちた変遷が解き明かされていく。
その中でも出色はゴルフ用具の進化について書かれた章だろう。「イギリスで最もインスピレーションをもたらす科学者」とされる著者は、ゴルフの力学に関する博士号も持つだけあって、ゴルフボールのディンプル(くぼみ)の秘密やグリーン上でピタリと止まるバックスピンの回転数など、ゴルフ好きならずとも知的好奇心を刺激してやまない話題が詰め込まれている。
〝目から鱗〟の物語を読み進めているうちに、読者はきっとある思いを抱くはずだ。アスリートが日々、勝つために厳しいトレーニングに明け暮れている裏で、多くの研究者や企業がスポーツテクノロジーの開発にしのぎを削っている。アスリートの努力よりもテクノロジーの進化のほうがパフォーマンスへの影響力が強いこともあるのではないか?
揉めに揉めて開催された東京五輪は、果たしてアスリートの祭典だったのか、それともスポーツテクノロジーの祭典だったのか、改めて考えさせられた。本書を読めば、スポーツ観戦で一喜一憂するだけではない、一歩進化した〝スポーツを見る眼〟が身に付いていることを実感するはずだ。
(鈴木裕也・科学読み物研究家)
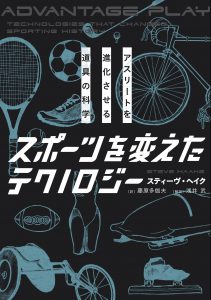
⇒noteで『スポーツを変えたテクノロジー』のはじめにを試し読みいただけます
白揚社だよりVol.9
*クリックすると拡大して、お読みいただけます。ぜひ他のコンテンツもご覧ください。
表